The best study method for you is..
あなたにおすすめの学習方法は..
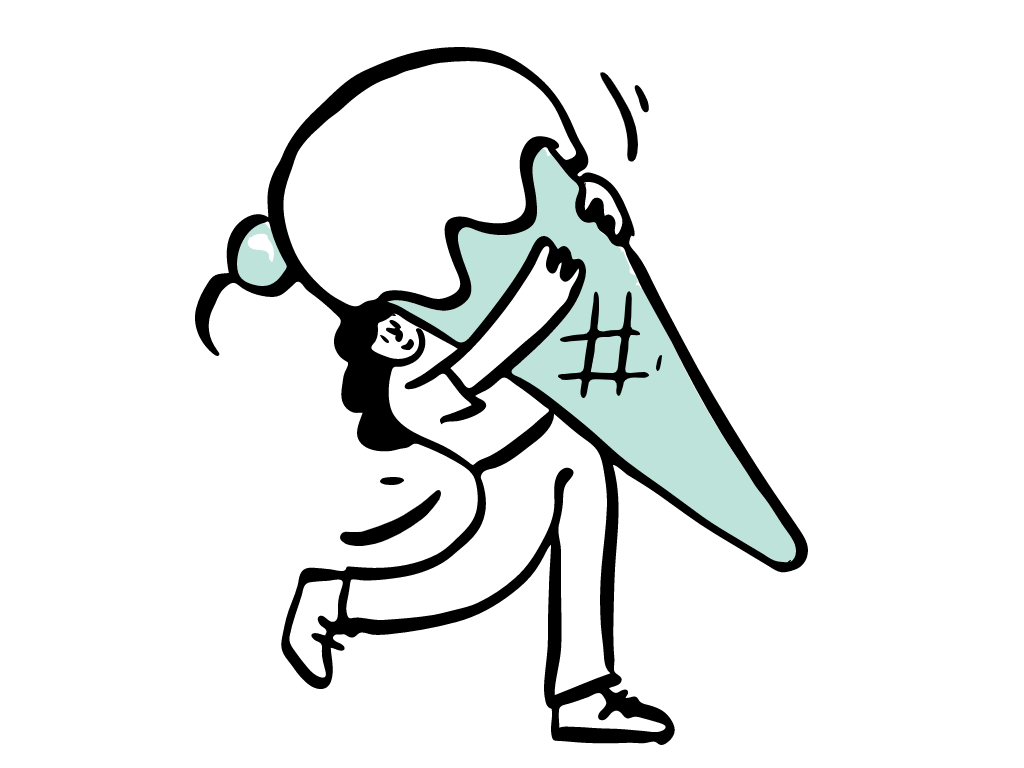
1. 単語やフレーズを分散学習で効果的に覚える
2. 幅広い分野の英文を読む
3. 分からなくても読み進める癖&前後から推測するスキルをつける
対策として、基礎的な語彙や文法の知識があれば、読んでいる文章に知らない単語や専門用語があっても練習次第で前後の文脈で想像できるようなスキルを身に付けることが出来ます。また、幅広い語彙を増やすことも大切ですが、知らない単語があったり、100%理解できなくても先に進めるようなマインドを持つことや、普段からいろんな分野の文章に触れて英文を読む耐性をつけることも大切です。
1. 単語やフレーズを分散学習で効果的に覚える
単語やフレーズを覚えたい時は「分散学習」がおすすめです。分散学習とは、一定期間の間隔をあけて繰り返し復習する方法。まずは1日後、覚えてきたら3日後、1週間後と復習の間隔を少しずつ空けていき、短期記憶から長期記憶に移していきます。
この時、単語やフレーズの習熟度によって復習間隔を管理するのがとても面倒なのですが、今は便利なアプリがあるので利用しましょう。
おすすめアプリ
分散学習帳
メンタリストのDaiGoさんが監修&制作の単語帳アプリ。自分でカードを作成でき、それぞれにURLや画像も添付可能。カードの復習回数や復習時の「回答の思い出し易さ」によってベストなタイミングを計算し復習させてくれます。プッシュ通知設定で日々の学習のリマインドもしてくれます。
Spaced Repetition by Wärn
シンプルな作りで、登録したいカードの表面、裏面ともに好きな色で文字を入力したり、画像を貼り付けしたり、直接文字やイラストを描いたりと自由度の高い単語帳です。分散学習帳と同様にリマインド機能があります。
ワンポイントアドバイス
さらに記憶に定着させやすくするために、アプリに登録する時のポイントがあります。
・新しく学んだ単語や表現を使って自分で例文を作って載せる
(難しい場合は辞書の例文をコピーする)
・イメージしづらい単語は画像を貼る
例文は自分が使いそうな場面や自分に関することだと尚良いでしょう。自分に関する内容だと他人のものより記憶に残りやすいからです。また、自分に関係のない例文や辞書の例文でも、文脈と単語が紐づけられるので、訳語のみより効果的です。また、単語にまつわるイラストや写真といった視覚的イメージも記憶を強化するのにおすすめです。
2. 幅広い分野の英文を読む
自分の興味がある分野や馴染みのある分野だけでなく、たまには異なる分野の文章も読んでみましょう。単語の知識だけでなく、内容としても新しい学びがあるはずです。新しく知ったことなどがあれば、それを誰かに伝えるイメージで要約するのもおすすめです。オンライン英会話などを受講しているのであれば、そこで話すのもいいですね。特にTOEFLや英検など様々な分野の長文を読む試験を受ける方は、日ごろから色んな分野の文章を読むことに慣れていると良いです。
基本的には自分の興味・関心のある内容の方が動機づけにつながり長続きもします。また、面白いと思って読んだ文章は、可もなく不可もなくというものに比べて内容の定着率が1.15倍に上がるという研究データもあります。そのため、基本的なリーディングのスキルアップは興味のある分野の文章をどんどん読むこと、そこにスパイスを加えるような感じで他分野の文章も読むのが良いでしょう。
おすすめリーディング教材
初級向け:News in Levels
簡単な診断テストで現在のレベルを明らかにし、自分のレベルに合った英文のニュース記事で読むことができるウェブサイト。同じ内容を音声(YouTube動画なのでスピード調整可能)で聞くことも。初級レベルからあるので初心者でもとっつきやすいです。
中級向け:Engoo Daily News
DMM英会話で使われる教材ですが、自習にも使えます。様々な分野の記事が6段階のレベルに分かれて書かれています。ディスカッションのための質問もあるので、答える形でスピーキング・ライティングの練習にも。またスマホやパソコンに音声読み上げ機能があればスピーキング・リスニングの練習もできます。(iPhoneでの音声読み上げ機能の使い方はこちらから)
上級向け:The Japan Times
言わずと知れた、日本のニュースが英語で読めるウェブサイト。最新の政治・経済ニュースからカルチャー情報など幅広い分野の文章が読めます。
上級向け:Vox
アメリカのニュース解説サイト。幅広い分野の英文記事が読めます。CNNやThe New York Timesといったニュースサイトに比べてやさしい英語で書かれています。
3. 分からなくても読み進める癖&前後から推測するスキルをつける
分からない単語があってもとりあえず読み進める癖をつけること、そしてすぐに辞書で調べず前後の文脈から想像するスキルを身に付けましょう。
<手順>
❶ 使われている単語の8~9割くらい理解できる文章を用意する。
❷ 単語を調べたり、返り読みをせずにできるだけ速く文章を読んで、その時間を計る。
❸ 同じ文章をゆっくり読み、分からない単語があれば前後の文脈からどういう意味かを、まずは推測。その後、辞書で調べて答え合わせをする。
❹ ❷より速い記録を目指して、もう一度速読する。
※❸で調べた知らない単語やフレーズは、忘れずに「1. 単語やフレーズを分散学習で効果的に覚える」で紹介した方法で覚えるようにしましょう。
<手順>
以下の手順❷❹❺❻はすべて時間を計りながら行ってください。
❶ 使われている単語の8~9割くらい理解できる文章を用意する。
❷ 単語を調べたり、返り読みをせずに"いつものスピード"で文章を読んで、その時間を計る。
❸ 同じ文章をゆっくり読み、分からない単語があれば前後の文脈からどういう意味か、まずは推測。その後、辞書で調べて答え合わせをする。
❹ <速読1>内容を意識しながら、できるだけ速めのスピードで読む。
❺ <速読2>"❹の1.5倍"(かかる時間は3分の2)を目指して、できるだけ速めのスピードで読む。
❻ <速読3>"❹の2倍"(かかる時間は2分の1)を目指して、できるだけ速めのスピードで読む。
<記録方法>
効果測定のためWPMを記録しましょう。WPMは"Words Per Minute"の略で、1分間に読める単語の数を指します。エクセルやGoogleのスプレッドシートを使えば、以下の計算式を登録でき毎回計算しなくていいので便利です。
・WPMの計算方法
文章全体の単語数 ÷ 読むのにかかった時間(秒)× 60
(例)284単語の文章を120秒で読んだ場合
284 ÷ 120 × 60 = 142 (WPM: 142)
<参考書籍>
『学校では教えてくれない!1か月で洋書が読めるタニケイ式英語リーディング』谷口恵子著(プチ・レトル)
おすすめリーディング教材
「2. 幅広い分野の英文を読む」で紹介した教材に加えて、以下もご参照ください。
<書籍(有料)>
全レベル向け:ラダーシリーズ
5つのレベルに分かれており、自分のレベルに合った本を豊富なジャンルの中から見つけることが出来ます。巻末に単語のリストがついているので、知らない単語があってもすぐに調べられます。有料ですがオーディオブックもあるので、併せて使えばスピーキングやリスニングの練習にも効果的です。
全レベル向け:Penguin Readers
8つのレベルに分かれており、自分のレベルに合った本を豊富なジャンルの中から見つけることが出来ます。Penguin Books社から出ている歴史のある書籍で、大きな書店やAmazonなどで購入できます。書籍によってKindle版もあります。